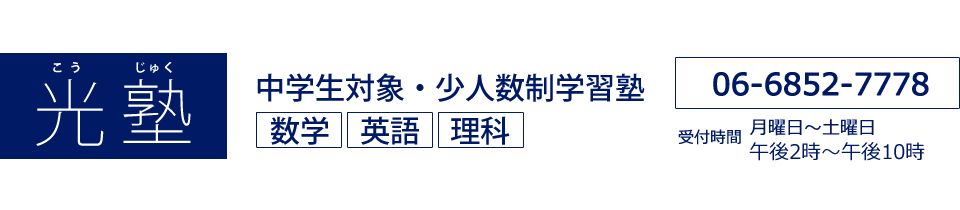3年生の1学期には多くの学校で生物分野と化学分野を学習する傾向があるように思います。化学分野ではイオンを中心に勉強しますが、ここでつまずく生徒が多くみられます。そこでイオンの分野前半のポイントを少し書いてみようと思います。イオンと言うとすぐに思い浮かぶのはテレビのCMで有名な「マイナスイオン」ですが、これは理科で勉強するイオンとは別のもので「空気中に浮かんでいるマイナスの電気を帯びた粒子」ぐらいに思っておくのが無難でしょう。
先ずポイントの1つ目は「イオン」です。イオンは2年の時に勉強した原子が電子を放出したり取り込んだりして正電気や負電気を帯びたもので、陽イオン,陰イオンと言います。これらのイオンは電解質が水に溶けて水溶液の中に生じるもので、自由に動き回れる状態にあります(電離)。だからイオンに関する化学反応は水溶液の中で起こっています。教科書に出てくる陽イオン・陰イオンの記号は覚えましょう。
ポイント2つ目は「電気分解」です。陽イオンや陰イオンがある水溶液に電極を入れます。すると陽イオンは陰極に引き寄せられ、陰イオンは陽極に引き寄せられます。これは同じ種類の電気は反発して、異なる種類の電気は引き合うということから分かります。電極についたイオンは電気を失って元の原子に戻って、原子によっては複数くっついて分子になって電極に出てきます。このとき出てくる物質の種類によっては水に溶けたり、反応したりするので注意しましょう。塩化銅・塩酸の電気分解は覚えましょう。
ポイント3つ目は「電池」です。陽イオンになるのはほとんどが金属です(教科書に出ている金属以外の陽イオンは水素イオンとアンモニウムイオン)。金属の種類によって陽イオンになろうとする強さに大小があり(イオン化傾向)、教科書では大きい順に Na Mg Al Zn Fe Cu Ag C(アルミニウムと炭素を使った電池が教科書にあるので付け加えました。)となっています。ここで2種類の金属を電解質の水溶液に入れて抵抗のついた導線でつなぐと、イオン化傾向の大きい方の金属がイオンになって溶け出し電子を金属板に残します。この電子が導線を通ってイオン化傾向の小さい方の金属板に移動して水溶液中の陽イオンと結合します。電流は電子の流れとは逆なので電流はイオン化傾向の小さい金属から大きい金属に流れたことになります。すなわちイオン化傾向の小さい方が電池の陽極と言うことになります。異なる2種類の金属と電解質溶液で電池ができます。そして、イオン化傾向の小さい方の金属が陽極になる。